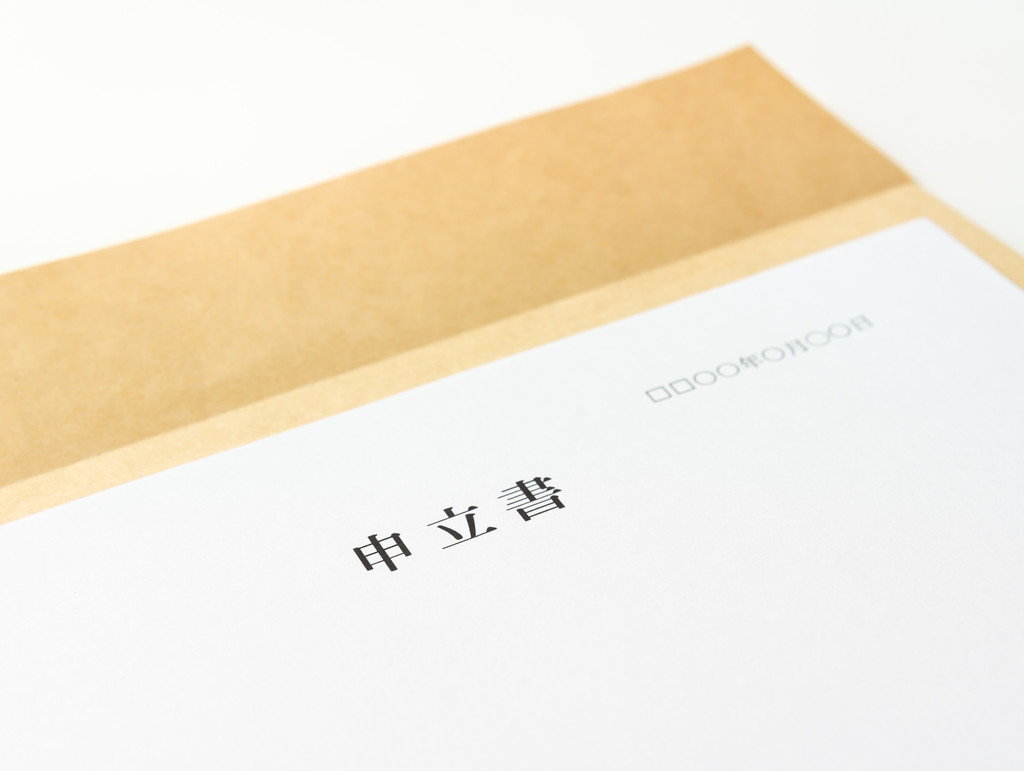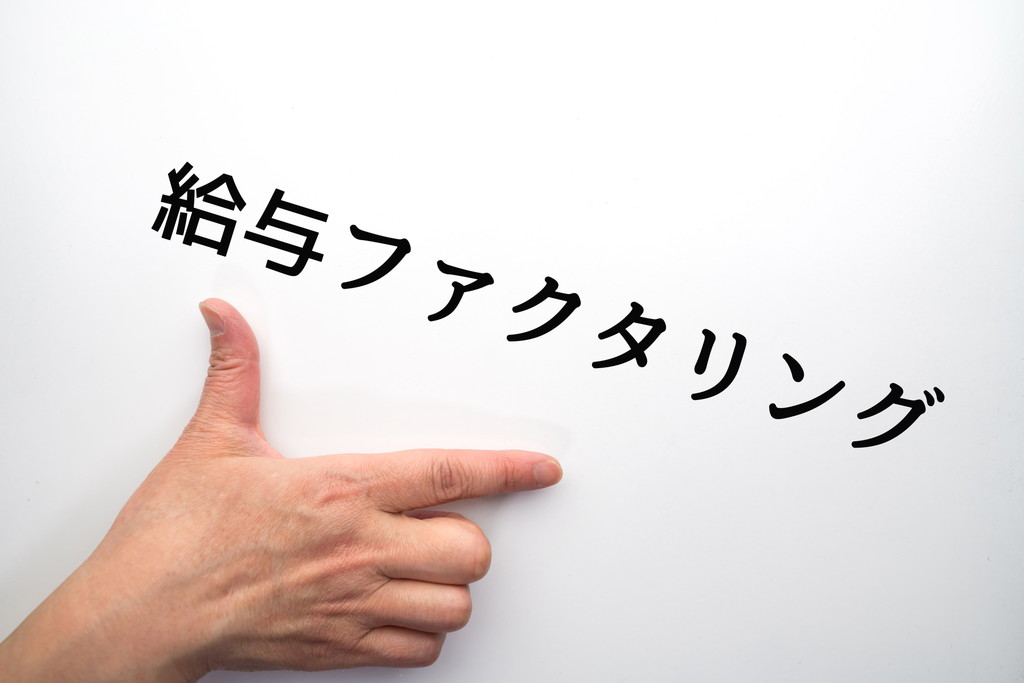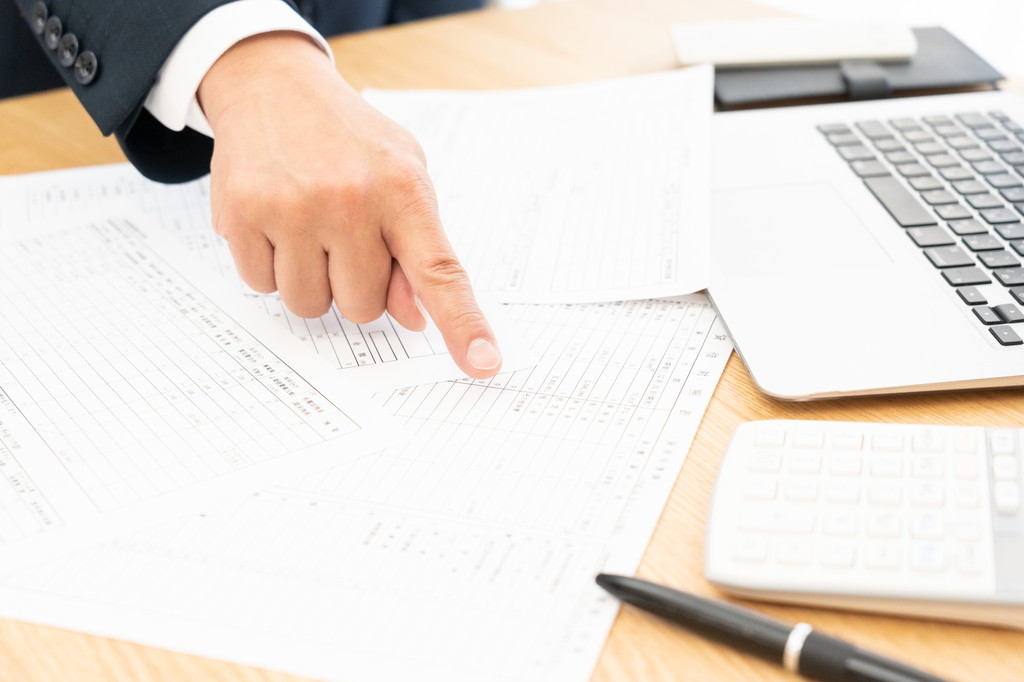特別清算と破産はどちらも清算型の債務整理ですが、名称以外にもいくつか違いがあります。そして、破産は聞いたことがあっても特別清算については初めて聞く方もいるのではないでしょうか?
そこで本記事では、「特別清算と破産の違い」や「特別清算のメリット・デメリット」などをお届けしていきます。
Contents
特別清算手続とは?
特別清算とは、株式会社に債務超過の疑いがある場合や清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合に、適正な清算のため裁判所の監督下で行われる清算手続です。特別清算には協定型と和解型の特別清算手続があります。
和解型の特別清算手続とは?
和解型の特別清算は債権者集会を開催せず、会社と債権者との間で個別に和解契約を締結して清算する方法です。
弁済に関しては、締結した和解契約に基づいて債権者に弁済することになりますが、債権者ごとに和解の内容が異なっても問題はありません。ちなみに、和解型の特別清算手続は、債権者の数が多い場合にはまず選択されることはありません。
協定型の特別清算手続とは?
協定型の特別清算は、債権者集会の決議と裁判所の許可を受けた協定に基づいて会社の清算をする方法です。債権者集会の可決要件は、出席議決権者の過半数の同意と、総債権額の3分の2以上の同意が必要です。
債権者と協定を結ぶことで一部の債務免除を受け、財産を換価処分して得た現金で弁済して清算します。この協定は、債権者と債務者との間で同意を得られれば、どのような内容にすることも可能です。
清算と解散の違い
そもそも清算とは、会社が有する財産の全てを処理することで、債務を返済して消滅させます。清算と解散は混同しがちですが、それぞれの持つ意味は異なります。清算は財産を消滅させるのに対し、解散は株主総会により会社を閉じることを指しています。
ただし、解散の時点では完全に会社がなくなるのではなく、清算により財産を処理した後に会社は消滅することになっています。
特別清算と破産はなにが違うのか?
特別清算と破産は清算型の債務整理で、どちらも「手続き終了後に会社が消滅する」という共通点もありますが、以下のような違いがあります。
- 法律
- 手続きの手順
- 債権者からの同意
- 手続きができる対象
- 手続きの要件
- 資産の管理人
- 手続きの費用
- 期間
次の項目から、それぞれ見ていきましょう。
根拠となる法律
根拠法はその名の通り、法律に基づいた手続きを行う際にその根拠となる法律のことを指します。
特別清算と破産ではこの根拠法が異なり、特別清算は会社法、破産は破産法に基づいて手続きがなされます。
手順
特別清算と破産はどちらも裁判所を通して手続きを行い、財産の管理や調査をする人がいますが、その手順の内容が変わります。
特別清算の場合、清算人が財産と債権の内容を調査し、債権者の同意を得てから一部弁済します。一方で、破産手続きをする場合は管財人が財産の換価処分をして、裁判所の許可を得て債権者へ配当するため、債権者の同意を得る必要はありません。
債権者から同意を得るかどうか
特別清算は、協定型にしても和解型にしても債権者からの同意を得る必要があります。
協定型の場合は2/3以上、和解型は個別に交渉し全員の同意を得なければなりません。
破産は債権者の同意は不要ですので、仮に反対多数であっても手続きが進められます。
つまり、特別清算を希望しても、債権者から同意を得られずに破産手続きに移るというケースもあるのです。
利用できる対象
破産手続きは個人でも法人でも行えますし、会社だけでなく社団法人等でも利用できる制度です。
特別清算が利用できるのは、解散した株式会社という大きな違いがあり、有限会社や合同会社では行えません。
要件
要件は、その手続きに必要となる条件のことを指します。破産手続きの要件は、裁判所から支払い不能であると認められなければなりません。
その一方で特別清算の要件は比較的緩やかであり、債務超過状態が明確である以外にも、「その疑い」がある状態で手続きは可能です。
債務超過でなく支払い不能ではない場合でも、清算の遂行が難しいと判断されれば特別清算が利用できます。
資産を管理する人
特別清算で会社の資産を管理するのは清算人で、会社が選任できます。そして、その会社の弁護士や代表者が務めることもあります。
反面、管財人は完全に第三者の必要があり、裁判所が選定した弁護士が管財人として選ばれます。そのため、特別清算は会社が主導して清算できるというメリットがあります。
手続きの費用
手続きに必要な費用にも差があります。どちらの手続きも裁判所へ予納金を支払うのですが、破産手続きの管財事件の場合は数十万円かかります。特別清算の方が費用は安い傾向があり、協定型では予納金が5万円程度です。
期間
特別清算は破産と比べて簡易的な手続きで済むため、申し立てから手続き完了までの期間が短めという特徴もあります。
破産の場合短くて半年ほどですが、特別清算の場合は2ヶ月での手続きも可能です。
特別清算と破産のどちらを選ぶべきなのか
特別清算と破産の違いは分かりましたが、一体どちらを選ぶべきなのでしょうか?
特別清算を選んだ方がよい時について
特別清算を選ぶべきなのは、「(解散した)株式会社で、債権者から同意を得られる時」です。
このような特性から、親会社が子会社を清算する時によく特別清算が選ばれています。
破産を選んだ方がよい時について
破産を選ぶべき場合としては、
- 株式会社以外が清算をする時
- 否認権行使したい時
- 株主や債権者から同意を得られない時
などが挙げられます。
特別清算の要件とは?
特別清算と破産の違いの説明により、特別清算の概要について把握できたかと思いますが、ここからはより詳細にお伝えしていきます。まずは、特別清算の要件について見ていきましょう。
株式会社であること
特別清算手続が利用できるのは株式会社のみであり、特例有限会社や持分会社である合名会社・合資会社・合同会社は利用できません。
また、医療法人、学校法人等の非営利法人も利用できませんが、相互会社及び特定目的会社、投資法人については特別清算手続を利用することが可能です。(相互会社及び特定目的会社、投資法人は株式会社の特別清算手続に関する規定が準用されているため。)
清算中の会社であること
清算手続に入る典型的な場面が解散ですが、清算中の会社であることも要件となっているため、株主総会を開いて解散決議を行うなどしなければなりません。
債務超過の疑い
債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を上回る状態を指します。わかりやすく説明すると、会社の持っている全財産を処分しても債務を完済できないということです。
債務超過の疑いという要件は、債務超過に対する要件が緩和されていることを指しているため、明らかに債務超過に陥っている会社でも特別清算の申し立てが可能です。
債務超過の判断としては、解散時の貸借対照表上債務超過であれば要件として判断されることが一般的です。ただし、法律上は債務超過の状態がある程度継続的であることが必要です。
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情とは、裁判所が関与しない通常清算手続を開始している場合に、通常清算手続きを進めるのに著しい支障を来すこととされています。
例えば、債権者が多数存在する場合や会社の債権債務関係が複雑である場合、そして清算人が誠意をもって清算手続を遂行しない場合などがそれにあたります。
法人の特別清算のメリットとは?

続いて、法人の特別清算のメリットについて見ていきましょう。
特別清算のメリットその1:手続きの完了が早い
特別清算の手続きは6カ月以内に終わるケースがほとんどであり、また、特別清算の和解型では2カ月程度で終了するため、手続きの完了が早い点がメリットの一つとなっています。ただし、特別清算の手続きに1年以上かかることもあるため、必ずしも手続き完了が早くなるというわけではない点に留意しましょう。
特別清算のメリットその2:破産と比べると印象が悪くない
特別清算という言葉は一般的にあまり認知されていない為、破産と比べた場合には印象があまり悪くないのもメリットの一つです。
特別清算のメリットその3:弁護士に手続きを任せられる
破産手続の管財事件になった場合、自社が依頼した弁護士とは別に、裁判所から破産管財人が選ばれることになり、破産管財人(弁護士)が財産の調査や換価処分を行うことになります。
しかし、特別清算の場合であれば自社が依頼した弁護士にすべての手続きを任せられます。
特別清算のメリットその4:予納金が低額
東京地裁では予納金は5万円と低額です。
法人の特別清算のデメリットとは?
続いて法人の特別清算のデメリットについて見ていきましょう。
特別清算のデメリットその1:特別清算を利用できるのが限定されている
特別清算を利用するためには、株主総会の特別決議として総議決権の過半数の出席、および出席した株主の議決権数3分の2以上の賛成を得られなければなりません。
そのため、同族会社や完全子会社の場合でない限り、解散決議を可決させるのは難しいと言えます。
その上で、特別清算手続の実施のためには、協定案に対して債権額の3分の2以上の同意等が必要であるため、利用できるのが限定されてしまっているのです。もちろん、協定案が否決されてしまえば特別清算を利用することができませんので、破産を選択しなければならなくなってしまうのです。
破産は強制的な清算手段ではありますが、特別清算の場合は同意の上で成り立つ清算手段となっています。
債権者集会で否決された場合は、結局破産手続きを選択せざるを得なくなり二度手間になってしまうため、特別清算を選ぶか初めから破産を選ぶかは、ポイントになってくるでしょう。
特別清算のデメリットその2:未払い債権の一部を弁済する余力が必要
未払い債権の一部を弁済できる余力がなければ、同意は得られませんので、換価処分できるものがなく弁済がほとんどできない場合は、特別清算手続は利用できません。
つまり、同意が必要であるため債権額における意見の対立があれば利用できないということです。
特別清算のデメリットその3:社長が連帯保証人の場合は社長の債務整理が必要
破産手続でも同様のことが言えますが、社長が連帯保証人になっている場合には、個人の自己破産などによる社長自身の債務整理も必要になってきます。
特別清算の申し立て件数について
特別清算の申し立て件数は毎年300件前後となっており、破産の30分の1程度しかありません。破産に対して特別清算手続はあまり認知されていないことや、特別清算の要件が、申し立て件数の少なさにつながっていると考えられます。
特別清算の申し立ては誰ができる?
特別清算の申し立ては、債権者だけでなく清算株式会社の代表者である清算人にも申立権があります。
また、債務超過の疑いがあれば、清算人は特別清算の申し立てをしなければなりません。その他、清算中の会社に監査役がいる場合には監査役にも申立権がありますし、株主にも特別清算の申立権があります。
特別清算を検討するタイミングについて
特別清算する場合、中小企業であっても多額の費用が必要になってきます。経営が傾くなかでどうにか立て直しを図ろうと無理な借り入れを繰り返してしまうと、清算すらできない…という事態に陥ってしまうこともありますので、特別清算を検討するタイミングはとても重要です。
撤退のラインも考える
経営が傾き売上が減少しつづける中では、立て直しはもちろんのこと、撤退ラインを設けなければ再起も難しくなってしまいます。
法的清算ができる程度の資金が残っている段階で、経営が危ういなと思えば早めに弁護士など倒産・清算に詳しいプロに相談することをおすすめします。
協定方式の特別清算の流れ
続いて、協定方式の特別清算の流れについて見ていきましょう。
弁護士の受任通知
特別清算の申し立てを検討し、弁護士に依頼するとその弁護士は債権者に対して、代理人になったことを通知する受任通知を送ります。
受任通知を受理した債権者はその後、債務の返済を請求することができなくなります。そして、弁護士は会社の財産を保全するために、会社の通帳や銀行員、不動産の権利書、証券類などを保管することとなります。
書類の整理
会社が特別清算を行いたいと思ってもすぐに実行できるわけではなく、多くの種類を集め、整理することが必要になります。
特別清算を行うのに必要となる書類としては、確定申告書や会社の会計帳簿(売掛帳、買掛帳、総勘定元帳、金銭出納帳等)、リース契約書や金銭消費貸借契約書などの債務に関する契約書、社会保険料の通知書など多く存在し、弁護士が整理していきます。
また、訴訟問題にも発展する可能性があるため、依頼者や社長が換価処分可能である財産を隠したり処分したりしないように、確認しなければなりません。
解散決議・株主総会の開催
特別清算を行うには、まずは株主総会を開催して会社の解散決議を行います。解散決議は、株主の議決権の3分の2が解散に賛成した場合に可決されます。また、特別清算人の選任を決議することとなり、解散後は取締役に代わって、清算人が会社を管理します。
清算人の職務内容としては、
- 裁判所への申し立て
- 債権者に債権を届出してもらい負債を確定
- 会社資産の売却や回収
- 債務の弁済内容についての協定案の作成
- 協定が裁判所に認可されれば債権者に弁済を行う
などが挙げられ、弁護士もしくは経営者が就任することが一般的です。
申し立て~特別清算の開始
特別清算の申し立てを行うと、裁判所は特別要件を満たしているかを判断し、要件を満たしている場合には特別清算の開始となります。特別清算の開始と同時に株主総会で選任された特別清算人が就任し、会社が保有する財産を管理・調査して財産目録を作成します。
その他、協定の策定や債権者集会の招集などを行い、必要な手続きを進めます。
特別清算申し立ての際には申立書の他に、会社謄本、定款、解散決議の議事録、直近の決算書などの書類が必要です。
協定内容の実行
清算人が裁判所に協定案を提出したのち、裁判所で行われる債権者集会で協定案が認められると、裁判所が認可を決定します。そして、認可の決定後は協定内容の実行として債権者へ支払います。
特別清算の終了
協定通りに弁済が完了すれば裁判所は特別清算の終結を決定し、その後法人格は消滅します。協定で残債務の免除が定められていますので、特別清算が終結すれば会社の資産と負債は0になります。
まとめ:特別清算とは?破産との違いやメリット・デメリットを解説!
いかがでしたか?今回の内容としては、
- 特別清算手続は債権者との合意があって成り立つ清算手続である
- 特別清算手続には和解型と協定型が存在する
- 特別清算と破産は法律や要件、費用や手続きに違いがある
- 特別清算手続のメリットは破産と比べると印象が悪くない点や期間が短い点である
- 特別清算手続のデメリットは利用できるのが限定されている点
以上が覚えておくべき大切なポイントでした。
特別清算は破産と比べて、手続きや費用においても有利に働く面があります。しかし、利用する対象が限定的であること、債権者・株主から賛成を得なければならないことなどから倒産時に特別清算を選ぶ例はそれほど多くありません。
債務・債権の内情によってもどちらがよいかは異なりますので、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
経営者がまずは読むべきおすすめ記事
資金繰りとは?悪化の原因と資金ショート時の優先すべき支払い
会社破産手続きの流れ・仕組み・期間を徹底解説!|【倒産の基礎知識】
国が認めた借金救済措置とは?借金の減額・免除方法を徹底解説!
資金ショートとは?9つの原因と6つの対策を解説!
自己破産後クレジットカードは使えない?気になる疑問の真相!
自己破産後の生活はどう変わる?誤解多き破産の真実に迫る!
給料未払いは罪であり刑事事件にも発展!労働基準法違反はNG!
自己破産手続きの流れと期間!気になる費用も解説!
第二会社方式とは?第二会社方式の仕組み・メリット・注意点を解説!